中学数学テスト対策として、今回は「商と余りの関係について」のポイントと練習問題です。案外、商と余りの関係については知らない人や忘れてしまっている人も、多々いるので、ここでしっかりポイントをつかみ、テストで出題されたときに、解けるようにしていきましょう。
商と余りの関係のポイント
A÷B=PあまりQ ⇒ A=BP+Q
(例)15÷2=7あまり1 ⇒ 2×7+1=15
(例)15÷2=7あまり1 ⇒ 2×7+1=15
では、実際に問題を解いていきましょう。解説は、一番下にリンクを貼っていますので、そちらで確認してください。
商と余りの関係の練習問題
【中1(数量を式で表す)】(1)ある数aを8で割ると商がbで2あまる数となるとき、数量の関係を等式に表せ。
【中2(等式の関係)】(2)ある数aを8で割ると商がbで2あまる数となります。このとき、bをaを使った式で表せ。
【中3(数の証明)】(3)5n+2と5n+3の2つ整数の積を5で割ったとき、1余ることを説明せよ。
【解答】
(1)a=8b+2
(2)b=(a-2)/8
(3)(5n+2)(5n+3)
=5(n2++6n+1)+1
ここで(n2++6n+1)は、整数なので、
5×(整数)+1となり、1余ることがわかる。

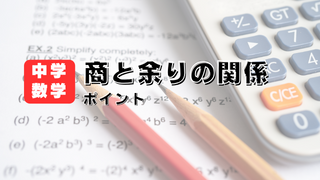
コメント