中学国語「徒然草(仁和寺にある法師)の練習問題」です。
徒然草(仁和寺にある法師)の問題
次の古文を読んで、後の問いに答えなさい。
<現代語訳>
仁和寺にいた、ある法師が、年をとるまで石清水八幡宮を参拝しなかった(したことがなかった)ので、 情けなく(残念に)思って、あるとき決心して、ただひとりで徒歩でお参りした。 (石清水八幡宮に属する寺の)極楽寺と、(石清水八幡宮の末社である) 高良神社などを拝んで、(石清水八幡宮は)これだけだと思いこんで帰ってしまった。 そして、同僚に対面して、「長年の間思っていたことを、なしとげました。 (石清水八幡宮は)(かねて噂に)聞いていた以上に尊くいらっしゃった。 それにしても、参拝した人がみんな山へ登ったのは、何事があったのだろうか。 (私も)行ってみたかったが、神に参詣することが本来の目的だと思って、 山(の上)までは見ない(で帰った)。」と言ったそうだ。 ちょっとしたことにも、案内者はあってほしいものである。
【問1】( )に適語を入れなさい。
【問2】次の古語を現代仮名遣いにしなさい。ただし、すべて平仮名で書くこと。
➊あやしう ➋詣(まう)でけり ➌尊(たふと)く
【問3】次の古語の意味を書きなさい。
➊つれづれなし ➋そこはかとなし ➌心うし ➍ゆかし ➎先達(せんだち) ➏あらまほし
【問4】なぜ石清水に参拝しようと考えたのか?
【問5】「ゆかしかりしかど」とあるが法師は、どんなことを「ゆかし」と思ったのか、簡潔に書きなさい。
【問6】「言ひける」とあるが、誰が誰に言ったのか、( )に書きなさい。
(➊ )が(➋ )に言った。
【問7】「ぞ・なむ・や・か・こそ」という助詞があると、文末(結び)の形が変わることを何というか?
徒然草(仁和寺にある法師)の解答
【問1】➊鎌倉 ➋随筆 ➌兼好法師 ➍無常
【問2】➊あやしゅう ➋もうでけり ➌とうとく
【問3】➊退屈だ ➋何というあてもない ➌残念だ ➍知りたい ➎先導者 ➏あってほしい
【問4】老年になるまで参拝したことがないことを残念に思ったので。
【問5】参詣した人がみな山へ登ったのはどうしてなのかということ。
【問6】➊仁和寺にある法師 ➋かたへの人
【問7】係り結び
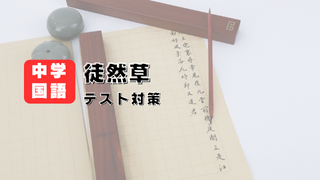
コメント