中学国語「枕草子の練習問題」です。
枕草子の問題
次の古文を読んで、後の問いに答えなさい。
春はあけぼの。➊やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる。
夏は夜。月の頃は➋さらなり、闇もなほ、蛍のおほく飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、➌ほのかにうち光りて行くも、をかし。雨など降るも、➍をかし。
➎秋は夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近くなりたるに、烏(からす)の、寝所(ねどころ)へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへ、あはれなり。まいて、雁(かり)などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。
日入りはてて、風の音、虫の音など、はた、言ふべきにあらず。
冬は早朝(つとめて)。雪の降りたるは、言ふべきにもあらず。霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎおこして、炭持てわたるも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるく➏ゆるびもていけば、火桶(ひおけ)の火も、白き灰がちになりて、➐わろし。
<現代語訳>
春はほのぼのと夜が明ける明け方。だんだんとあたりが白んで、山のすぐ上の空がほんのりと明るくなって、淡い紫に染まった雲が細くたなびいている様子が趣があってよい。
夏は夜。月が出ていればもちろん、闇夜でも、蛍が多く飛び交っている様子がよい。また、ほんの一匹二匹、ほのかに光っていくのもよい。雨などが降るのもまた趣があってよい。
秋は夕暮れ。夕日が写しくて、今にも山の稜線に沈もうという頃、カラスがねぐらへ帰ろうと、三羽四羽、二羽三羽など思い思いに急ぐのさえ、(しみじみと心にしみる)。まして、カリなどで列を連ねて渡っていくのが遥か遠くに小さく見えるのはたいそう趣がある。すっかり日が落ちてしまって、風の音、虫の音などが様々に奏でるのは、言うまでもないほどに趣がある。
冬は早朝。雪が降り積もっているのはもちろん、霜が真っ白に降りているのも、またそうでなくても、はりつめたように寒い朝、火などを急いでおこして炭火を部屋から部屋へ運んでまわるのも、いかにも冬の朝らしい。昼になってだんだん寒さが緩むと火鉢の炭火も白く灰をかぶってしまってはよくない。
【問1】枕草子の作者名を漢字で書きなさい。
【問2】「➊やうやう」「➍をかし」を現代仮名遣いにしなさい。すべて平仮名で書くこと。
【問3】「➋さらなり」の現代語訳を書きなさい。
【問4】「➌ほのかにうち光りて」とありますが、何がうち光りているか答えなさい。
【問5】作者は、「➎秋は夕暮れ。」の趣のあるものとして何を挙げているか、すべて書き抜きなさい。
【問6】「➏ゆるびもていけば」の主語は何か答えよ。
【問7】「➐わろし」とあるが、作者は何のどんな様子を「わろし」と思っているか簡潔に書きなさい。
枕草子の解答
【問1】清少納言
【問2】➊ようよう ➋おかし
【問3】言うまでもない
【問4】蛍
【問5】烏、雁、風の音、虫の音
【問6】寒さ
【問7】火桶の火の白い灰ばかりになっている様子。

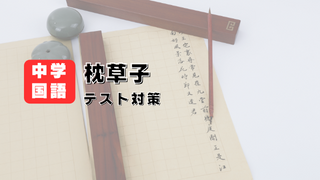
コメント